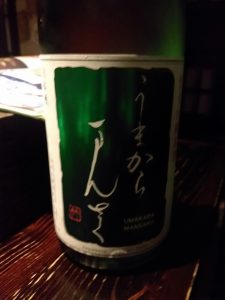STAFF BLOGスタッフブログ
スタッフブログのTOPへ
こんにちは 辰尾です。 先日、後楽園に仕事で出かけて来ましたが、その折に東京のど真ん中に歴史史跡として残っている広い庭園、小石川後楽園を散策して来ました。 12月も下旬に入っているのにまだ紅葉が残っていたのでびっくりしました。 先回の私の話はカエデとモミジは植物学的には同じカエデ科カエデ属に分類されていて違いは無いとの話をしましたが、この小石川後楽園では同じカエデ属の木が赤い葉を付けた木と黄色い葉を付けた木があったので、ちょっと不思議に思って調べてみました。 樹木の葉っぱには、もともと緑の色素クロロフィルと黄色の色素カロチノイドが含まれていて、秋になり日差しが弱くなり気温が下がると、緑色のクロロフィルが分解されて少なくなり、黄色のカロチノイドが残るため、イチョウなどの葉は黄色くなります。 一方、落葉樹は秋になると葉っぱと茎の間の栄養が行ったり来たりしないよう自ら葉っぱの付け根を遮断してしまいます。モミジなどの紅葉する樹木は、葉の中に光合成でできた糖分がたまりこの糖分が引き金となってアントシアンという赤い色素が合成され、葉っぱが赤く色づくということだそうです。しかし、同じ一本の木でも日光の当たり具合で赤い葉と黄色い葉が同居したりしていますし、同じ種類のモミジでも日当たりの条件が違うと赤い葉の木と黄色い葉の木が存在することもあるのだそうです。この小石川後楽園のモミジの木が赤と黄色だったのは日当たりの条件の違いなのかなと納得をしました。
今年も残すところわずかになりましたが、皆様には大変お世話になりました。有難うございました。
今後とも、皆様のお役に立てるようニーズを先取りした独自商品の開発に取り組み、取り扱い商品を増やして、さらなるサービス向上に努めてまいります。
来年も変わりませずご愛顧の程をお願い申し上げます。
こんにちは、藤田です。
12月に入ると世間はクリスマス、年末へと気分的に慌ただしく加速していきます。
先日、仕事帰りにアクアパーク品川という水族館に立ち寄りました。
実は年間パスポートを利用し、たまに大人の寄り道をするのが密かな楽しみなのです。
↓品川駅を降りるとホテルの窓のクリスマスツリーのイルミネーションが目を引きます。
水族館としては大きくありませんが、季節ごとに展示を変えているので違った雰囲気を楽しめます。
クリスマスのイメージで装飾した水槽の絵本のような空間にフグの仲間?が泳いでいます。
イルカショーはウォーターカーテンとプロジェクションマッピングを駆使して視覚的に見応えがあります。
皆さんも忙しい年の瀬ですが風邪に気をつけ(たまに息抜きをして)良いクリスマスをお過ごしください。
こんにちは。 辰尾です。
先月、甥の結婚式がありまして北海道の帯広に里帰りして来ました。
東京はまだノーネクタイのクールビズが続いていましたが、帯広では最高気温が一桁台にまでなっていて、東京の冬の気温に近い状況だったので、ヒ―トテックやコートの冬装備で行こうか?迷いましたが、東京での秋バージョンで行くことにしました。幸い滞在中は秋晴れの良い天気でしたので心配は無用でしたが、それでも朝晩は身体が引き締まるような冷たい空気でした。次の日に少し余裕があったので、ちょうど紅葉が見ごろの名所に案内してもらいました。帯広郊外にある福原山荘です。北海道で一番標高の高いカルデラ湖である然別湖へ向かう直前の登坂道から分かれて、平らな道路を2km程進んだところに福原山荘があります。ここは十勝地方でスーパーマーケットを展開している創業者の山荘で、紅葉の期間だけ一般開放しています。8.5haにも及ぶ広大な敷地内には5つの滝と、3つの池があり、そして、それらを巡る全長1kmの散策路沿いに1000本のモミジが植えられています。10月の中旬過ぎに、赤・黄に色付いた木々の中を散策しましたが、ゆったり流れる時間を感じて来ました。モミジと青空を映した池は鏡を観ているようで、とても感動しました。
さて、モミジとカエデは違うのか?について少しお話をさせて頂きます。
植物分類上ではカエデとモミジの区別はありません。 植物学的にはモミジもカエデも「カエデ」と言い、どちらも分類上カエデ科カエデ属の植物です。モミジという科や属はありません。モミジとカエデを区別しているのは日本人だけで、外国ではカエデ属の植物を全て「maple」と呼んでいます。英語ではもみじを「Japanese maple」と表記しますが、直訳すると「日本のカエデ」となります。モミジもカエデも同じカエデ属の植物ですので分類学的に言えばカエデという大きなくくりの中にモミジという種の群があるイメージです。
しかし、日本では園芸や盆栽の世界で特有の区別基準があるようです。
園芸 モミジ:葉の切れ込みが多く、深いもの。イロハモミジ、ヤマモミジ
カエデ:葉の切れ込みが浅いもの。トウカエデ、イタヤカエデ
盆栽 モミジ:葉の形が小さくて切れ込みが深く。秋に真っ赤になるもの。
カエデ:葉の切れ込みが浅くて、大きいもの。
と区別しているそうです。
11月も中旬になるとまち中でも街路樹が色づき始めました。紅葉の名所では、すでに大勢の人で賑わっていることと思います。皆さんも是非、空気の澄んだ青空の下で紅葉を愛でてゆったりとした時間を過ごしてみて下さい。
こんにちは、藤田です。
秋も深まりましたが、今年のハロウィンも盛り上がりを見せたように感じます。
こちらはジャック・オー・ランタンならぬハロウィン柿(スーパーに並んでいました)
お隣はハロウィンりんご(シールを貼って自作)です。
手軽にハロウィン気分を味わえ、後で食べられるお得感があります。
世間ではコスプレやパーティーを楽しむ若者が増えているようですが、
縁のない私は普段と変わらず日本酒でハロウィンを祝いました。
金目鯛の干物と亜麻猫スパークですっきり喉を潤します。
ムロアジには第3回酒1グランプリで優勝した和歌山の酒蔵の「紀土(きっど)純米酒」
やや辛口で一口飲んだだけで山田錦のうまみが伝わってきます。
バルコニーでは夏に植えた草花がだんだん枯れて寂しくなっていくなか
ハロウィン色に近い?ランタンならぬランタナの花が元気に咲いていました。
こんにちは 辰尾です。
いつも街路とか公園の散歩で樹木の話題でしたが、今回は横浜の自宅から日本橋に出かけて、まちなかを散歩した話題をご紹介します。コレド室町で9月の末まで開催されていました「アートアクアリュ―ム」と言う芸術的な金魚の展示会を観て来ました。今年で10回目の開催になるそうで、大変な賑わいでしたし、初めて見る驚きも大きかったです。
お昼すぎに横浜の自宅を出て15時頃地下鉄の三越前で降りたのですが、改札を出てすぐ長蛇の列が目に入ってきました。目的のイベントの列じゃないよなと思いながら先頭の方に行ったらまさに「アートアクアリュ―ム」の入場を待っている列で、スタッフが2時間半待ちと言うプラカードを持っていました。まだ30℃が続いていた時期で、並んでいる通路は冷房も入っていなく団扇や扇子が涼を取る唯一の手段でした。
この段階で「2時間半も待つのは、とっても無理」との結論を出して、映画を観て帰る事にしました。同じビルの3階にあるTOHOシネマズに行ったら、ちょうど観たかった「BFG(ベスト・フレンドリー・ジャイアント)」をやっていて20分程で始まる処だったのですぐ入場しました。小女と巨人のふれあいを描いたヒューマニズムあふれるストーリーでした。映画を観終わって出てきたら(ちょうど2時間半程)、長蛇の列が無くなっていて30分待ちになっていました。せっかく来たのだから30分くらいだと待ってもいいかと気が変わり列に加わりました。
普段観る事が出来ない金魚の珍しい種類が結構ありました。又、金魚を入れている容器も色々工夫されていましたし、その容器を浮かび上がらせる照明も工夫されていて幻想的でした。混雑の中でゆっくり観て回っても1時間はかからない会場ですが、水族館や一般的な展示場と違った雰囲気を味わいました。
来年にでも一度観てみたいと思われた方は、予約をしてから行くことをお勧めします。
こんにちは、藤田です。
シルバーウィークに入り暑さもようやく和らいできました。
久々に横浜の実家に帰り、ドアを開け家の中に入ると異様な匂いが・・・
その正体は↓
拾ってしばらくたった下処理前の果肉のままの銀杏&まるでベルコンの上に置かれたような殻付き銀杏です。
夜明け前に近所を散歩すると、街路樹の1本のイチョウの木の下に銀杏が転がっているのです。
昼間にも立ち寄りましたがすでに誰かに拾われたのか(笑)2個しか落ちていません。
2本あるイチョウのうち手前の銀杏が落ちているほうが雌の木のようです。
封筒に殻付き銀杏を入れ軽くレンジすると殻が割れむきやすくなります。
中身はきれいなヒスイ色をしています。
そのままでも十分いけますが、塩竈の藻塩を少しつけて冷酒をいただきます。
今宵の酒は「墨廼江ひやおろし」、石巻の酒です。秋の味覚に舌鼓をうちました。
こんにちは、辰尾です。
先日の日曜日には車で遠出をして石神井公園を散策して来ました。自然が多く残っていると言う評判なので、以前から一度観てみたいと思っていまして、先日の日曜日にやっと実行することが出来ました。
石神井公園は東京都練馬区にある都立公園で、園内には、石神井池、三宝寺池があります。井の頭池、善福寺池と並び、武蔵野三大湧水池として知られていまして、それを1959年に市民が散策できる公園として整備し、自然や野鳥と共存できるように造られたものです。今回は三宝寺池周辺を散策したのですが、園内には、野鳥や沼沢植物群(部分的に水でおおわれた湿 地帯に生える植物。カキツバタ、ミツガシワ、等)や雑木林が見られ、武蔵野と言う原野を想像させる面影がたくさん残っていて、とても東京23区内とは思えないほど緑豊かなところだと感心しました。
しかし、一番驚いたのは石神井公園内にブナの木を見つけた事です。ブナは、東北の白神山地のブナ林が世界遺産として有名ですが、関東においては標高の高い場所にしか見られない樹木で、丹沢でも標高600~800m以上の尾根筋にみられ、低地には存在しないものと思っていました。
びっくりです!!!
石神井公園は標高わずか50m程ですがそこにブナが存在するとは???
戻って調べてみたら森林技術センターから低地に存在するブナ林の調査報告書が出されていて、茨城や栃木の標高100m程の低地を調査したもので、その本数や分布域を記載していましたので、標高50m程の石神井公園にブナの木があっても不思議ではないのだと納得しました。


ブナは、木材として木目が通らず、腐りやすく狂いも大きいため、建築用材としては使えなく(漢字は木で無いと書く)伐採もしてこなかったので、低地でもブナ林が多くみられました。しかし、1950年代から始まった拡大造林政策(経済発展に伴う木材需要に応えるため、国内のブナ林を大規模に伐採して、利用価値の高いスギなどの針葉樹に植え替えを推進する)によってブナは壊滅的な打撃を受けたのでした。
石神井公園のブナは、この戦後の大規模伐採から逃れた貴重な樹木だと言う事が分かりました。それから、ブナは肥沃な土壌に生育しますが成長は遅く、5年たっても樹高1m程にしかならない樹木で、直径が40cmになるのに100年かかると言われています。したがって、石神井公園のブナは100年以上の樹齢だと推定出来ます。
もし機会があれば、石神井公園を散策してブナの木を探してみて下さい。伐採の危機を乗り越え100年以上も生きている幸運な樹です。
こんにちは、藤田です。
夏季休暇中は比較的涼しいうちの早朝散歩が日課でした。
内川沿いに歩いて行き、第一京浜国道を渡り、旧東海道から再び川沿いに入り水門を過ぎると河口に出ます。
大森ふるさとの浜辺公園は大田区立の海浜公園です。
人工の白い砂浜が広がりますが釣りや遊泳は禁止です。両端の岩場ではハゼ釣りをする人も見られます。
また、遊歩道ではスマホ片手にポケモンGOに熱中しながら歩いている人たちもちらほら・・・
公園の近くには大森海苔のふるさと館があります。ここでは東京湾の埋め立てまで海苔の生産で栄えた歴史などを
展示で学ぶことができます。冬期は「海苔つけ体験」が出来ます。私も以前参加したことがありますが、最初は
なかなか要領がつかめず3回目でうまくいきました。後日焼き海苔にし、自分で作ったおにぎりの味は格別でした。
海苔のふるさと館前の海苔乾し場↓ 波打ち際にまれにアカエイ(毒針注意)が泳いでいます↓
こんにちは、辰尾です。
休みの日には散歩をする事があると以前のブログで書きましたが、先週の休みにもいつものルートとは違う道を散歩してみましたらやはり違った景色が目に飛び込んできました。それは、背丈の高い樹木「ケヤキ」で作られた樹木のトンネルでした。私が住んでいるのは東急沿線の青葉台ですが、その一つ手前の藤が丘駅から延びている並木道で、我が家から青葉台駅とは反対方向に歩いて10分程の所にあるので青葉台よりちょっと近いところにあります。
ケヤキはニレ科ケヤキ属の落葉高木で、ケヤキの名は「けやけき木」からきたものです。古語辞典によれば「けやけし」は際立ってすぐれている事を意味するのだそうです。
全国的には並木道で一番多いのがイチョウ並木で、このブログでも「東大構内のイチョウ並木」「大阪御堂筋のイチョウ並木」を紹介しましたがその他にも明治神宮外苑や北海道大学構内のイチョウ並木が有名です。二番目に桜並木です。そして三番目に多いのがケヤキ並木だそうです。ケヤキは多くの自治体が「県の木」や「市の木」に指定していまして、宮城県、福島県、埼玉県は県のシンボル樹木となっていますし、その他にも78の市町村がシンボル樹木に指定しています。私が住んでいる横浜市もシンボル樹木としてケヤキを指定していまして、この「みたけ台のケヤキ並木」はその代表格として紹介されていました。
樹木のトンネル ケヤキの葉
他にも有名なケヤキ並木として、仙台市の定禅寺通りの4列もある街路樹とその樹木を100万個のイルミネーションで飾った光のページェントがあります。さらに、さいたま市の国道463号沿いの17㎞も続く日本最長のケヤキ並木等があります。
ケヤキ並木は、桜並木のように華やかではありませんが、暑い夏には木陰を作り涼しさを感じさせてくれますし、紅葉の時期には葉を黄色や紅色に変色させ代表的な秋の風景を作り出します。
私も、これらの有名な並木道を機会があれば是非観てみたいと思っています。
こんにちは、藤田です。先週末に秋田を訪れました。
秋田駅に到着すると「あきたびじん?」いやいやよく見ると「あきたびじょん」のポスターが・・・
これは「高質な田舎」を前面に出す、秋田県イメージアップ推進のユニークなキャッチコピーなのです。
しばらく歩くと千秋公園のお堀いっぱいのハスが目に飛び込んできます。あれ、葉の上に大きな水滴が・・・
気になり調べたら、ハスの葉は特殊な表面構造をしていてきれいに水をはじくのだとか(ロータス効果)
これを着眼点にし超撥水性を取り入れた製品も多く造られている等々初めて知りました。
前回に続き夜はやっぱりお酒です。
秋田では平成26年に「秋田の酒による乾杯を推進する条例」が制定されています。
私は東京でも日々実践を心がけていますが・・・
今宵の酒は「うまからまんさく」辛口ながら淡麗でなくコクと旨味を感じるお酒です。
肴はじゅんさい、カスベ煮、いぶりがっこ、いか塩辛 これさえあれば十分です!!
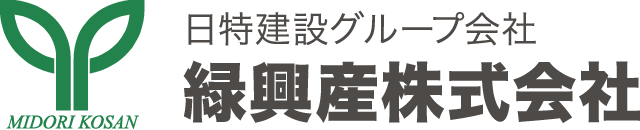

















-150x150.jpg)